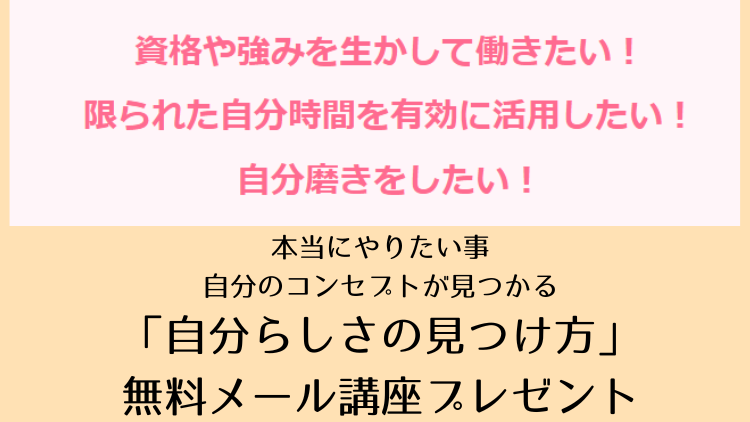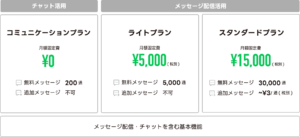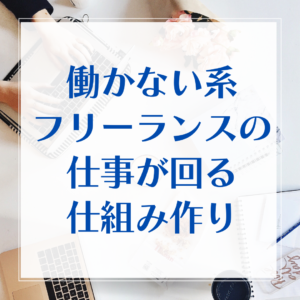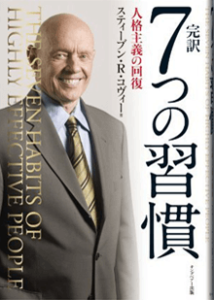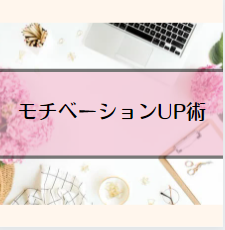こちらのコラムは子育てママに役立つ情報を色んな講師から学ぶコーナーです。
今回は、小学生ママやこれから小学生ママになる方に是非聞いて欲しいお話。
身近なようで身近じゃない。当事者にならないと見えない課題について語って頂きました。
ある日突然、子供が学校に行きたくないと言い出したら??< h2>
について、ご自身の経験を語って頂きました。

 < p>
< p>
みなさま、はじめまして!< p>
ジブン資産化パーソナルトレーナーの伊藤みみこと申します。< p>
企業の健康保険組合で10年にわたり社員向けの健康相談や健康啓発活動をしてきました。< p>
このノウハウを活かして、アクティブに人生を過ごしたいママやパラレルワークを目指す方に向けた健康づくりサービスを提供しています。< p>
さて、みなさんは朝お子さんに< p>
「学校行きたくない」< strong>< blockquote>
って言われたことがありますか?< p>
「不登校や行き渋りはもはや珍しくない」< strong>< p>
「不登校は問題行動ではない」< strong>< p>
とニュースでは聞くものの、実際目の前にその事実が突き付けられたとき、やっぱり最初はショックを受けてしまう人は多いのではないでしょうか。< p>
私は3人の子どもの母親でもあるのですが、長男は小学校入学当初から学校になじめませんでした。さまざまなタイプのクラスメイトや上級生、そして先生を押しのけて子どものコミュニケーションに首を突っ込みまくる保護者・・・私も学校をとりまくコミュニティにびっくりしましたが、長男本人がいちばん傷ついていたことでしょう。< p>
そして初めて「行きたくない」と玄関で泣かれたのが1年生の3学期でした。< p>
< p>
(photo by:mochi0830/写真AC)< p>
そのとき私が思ったのは< p>
「会社休めないのに・・・!」< strong>< span>< p>
なんとも自己中なショックの受け方ですが、会社員の私が学校に求めていたのが「日中の預かり先としての機能」だったのです。< p>
だからといってムリヤリ毎日引っ張って連れていくのがいいのでしょうか?< p>
ここから先は、私がそこから何年もかけて学び、実践していったことを書いてみます。< p>
学校が苦手な子どもは、まじめで優しく、怖がりな性格の子が多いといいます。< p>
小学校の雰囲気は、幼稚園や保育園とガラッと変わります。なにしろそこにいる人数に圧倒されますし、それによるトラブルも多いですよね。< p>
それを押さえるために指示や規則でしばられることも増え、不自由も感じます。< p>
どこに不安を感じるかはそれぞれですが、本当に不安で怖がっているということに共感してあげて欲しいと思います。< p>
そして可能な限り、そんな日は子供のしたいようにさせてあげて、一緒にできることはしてあげようと思いました。< p>
私は、一緒にお出かけしたってかまわないと思っています。保護者が付き添っているんですから。< p>
今になって私が反省しているのは、あのとき「会社を手放せない」と思ってしまったことです。< p>
当初からムリヤリ連れていくということは考えませんでしたが、休んだ日の代わりの預け先を探したり、教育相談室を利用したり、行かなくても済む方法を考え続けました。でも、自分も会社を辞めさせられないようにすることを前提にしていたのも事実です。< p>
そういう施設は平日の日中にアポイントを取るしかありません。そのため自分の休暇がみるみる減り、ついに欠勤になり、会社の人事から警告を受けました。仕事に穴をあけないなどは関係ない、毎日出社するべきだと。(このあたり、きわめて学校的ですね。)< p>
これに従うのも生活のために仕方がないと思っていましたが、あのとき素早く会社を辞めてもいいという覚悟ができていたら、もっと自分のビジネススピードも速かったかもしれません。< p>
そうすれば、子どものエネルギーが切れる前の段階で自宅が最後の安心安全の場として機能し、元気を取り戻すのももっと早かったのかもしれません。< p>
それがすぐにできなかった我が家では、長男は昼夜逆転の生活になり、用意した食事も最低限しか食べないという状態になりました。< p>
ここまできてやっと、自分の意識そのものをアップデートしないと問題に対応できないと気付かされたのでした。< p>
勉強面も何とかなる< h2>
子どもが学校に行かないというとき、< p>
「勉強についていけなくなってしまうのではないか?」< p>
「社会性(コミュニケーション力)が育たないのではないか?」< p>
< blockquote>ということが気になるお母さんも多いでしょう。< p>
でも昔ほど心配することはない、と今の私は思っています。< p>
今はたいへん良質な教育コンテンツがネットで配信されていますし、これからもその傾向は加速していくでしょう。< p>
コミュニケーションにしても、誰かとつながり、社会に交わる方法は格段に増えました。現在長男はよくネットゲームをしていますが、< p>
「今日のメンバー外国人だった」< p>
とさらっと言います。お互い全然言葉は通じてないのですが、意思疎通して普通にゲームを進めています。< p>
ネットゲームでは、たまに戦況が悪くなるとブツッと「落ちる」人がいます。残された人はゲーム内での迷惑をこうむるので初めのころはブチギレていた長男ですが、最近では「そんなもんだ、たかがゲームの世界のことだし」というのを学んだようです。< p>
不登校から学ぶ事< h2>
私たちが子どもに願うのは「幸せ」と「自立」ではないでしょうか??< p>
昔はそれを得るための唯一の方法が学校だったかもしれませんし、今でも学校は効率よくこれらを学べる場所だと思います。< p>
でも今は社会システムも多様化し、選択肢(効率は悪いかもしれません)が増えました。< p>
これまでのレールに乗って幸せに自立できる子もいればそうでない子もいて、それぞれにふさわしい方法を子どもたち自身が見つけていけばいいのです。< p>
お母さんはそのお手伝い、サポートをするという気持ちでお子さんを見守ってあげればいいのだと思います。< p>
ちなみに、「期待」と「信じる」は違います。< p>
期待は親の意志が主体です。< p>
信じるということは、子どものありのままの姿を受け入れて、その先の未来をおだやかに待つことです。< p>
そんな事を学べるキッカケになったのかもしれません。
不登校になったらどんな風に過ごしたらいい?< h2>
長男は3年生で完全不登校になりましたが、前回も書きましたが幸い(?)昼夜逆転で日中外出の心配がなく、食事を用意しておけば自分で食べるようになっていました。この頃になると少しラクになりました。< p>
不登校の子どもが増える中で、一般向けの資料も増えてきた時期でした。< p>
本やネットの記事を読むことで自分自身の視野を広げていくことができました。ネットには不登校ビジネスと呼ばれる怪しいものもあるので、信頼できるものを見定めるようにもしていました。< p>
親の会や支援団体の集まりにも参加しました。< p>
それぞれ学校復帰を目指すもの、自宅での生活を受け入れるもの、それぞれのカラーがあります。資料などを参考にして、直感でもいいので自分自身がいちばんおだやかな気持ちで参加できそうな団体を見つけていくといいでしょう。< p>
何より同じ悩みをもつ親同士のつながりを発見できるだけでも、とてもいいことだと思います。その中でもそれぞれの体験をシェアすることは、自分の視野を広げる大きなメリットになると思います。< p>
子どもが自宅で過ごしているとき、子どものネット使用にもアダルトコンテンツの制限はかけましたが、視聴時間の制限は最初からしませんでした。< p>
自宅ではゲームさえ手を付けずYouTubeだけを見ている時期がありました。ゲームは自分で動かさなければ進みません。それをする程度のエネルギーもなかったのだと思います。< p>
それでもYouTubeは彼にとって唯一の外とのつながりでした。< p>
そんなあるとき、< p>
「このゲーム入れたい」< p>
と言ってiPadを見せてきました。YouTubeの実況で見た無料ゲームをやってみたいと思えるようになった・・・主体性が復活してきた証です。< p>
その後もゆっくりとやりたいという気持ちを取り戻し、4年生になったころには昼夜逆転もなくなり、日中を私と公園で過ごしたりできるようになりました。< p>
また、教育センターや家庭支援センターにこちらから連絡を取るなど、支援機関を積極的に利用することで、自分のためのヘルプを出しやすくする環境をつくりました。< p>
その結果、私は会社にいるけれど子どもは自宅で過ごしているという状況を認めてもらえるようになりました。これは物分かりのいい相手に恵まれたのかもしれません。< p>
母として出来ること< h2>
でも、< a>どうしても子どもの動き(動かないことも含めて)が気になってしまう・・・。< p>
そんなときはまず自分自身に目を向けてみましょう。< p>
子どものエネルギーが極端に下がっているときに必要なのは手を引っ張ることでも背中を押すことでもありません。< p>
まずはお母さんがどんどん外の世界とつながって、楽しんでいる姿を見せてあげるだけでいいと思います。< p>
そして、自分のチカラで立ち上がった子どもがお母さん求めてきたとき、そのときにしっかり応えてあげてください。< p>
我が家の長男は相変わらず学校の雰囲気が嫌いだと言っていますが、< p>
「学校で勉強したいから」< p>
と登校することができています。< p>
自宅でも、ほぼ引きこもり状態になったあの日からは比べものにならないほど元気に過ごしています。< p>
4月になったからという流れのままに学校に行きはじめたのとは違い、一度離れて< p>
「なぜ自分は学校に行くのか」< p>
< blockquote>を自分で考えた結果行くことを選んだ子どもは、以前よりぐっと心が強くしなやかになっていると感じています。< p>
子どもたちと、自分自身のエネルギーを信じることが大切ですね。< p>
profile< h3>
親子で不登校を乗り越えてきた自身のブログで、子育て中のママやパラレルワーカーが人生をアクティブに過ごすコツなどを発信しています。< p>
ぜひご覧ください!< p>
< p>
Mimiko Project アメブロ支部< p>
https: ameblo.jp mimi-project-net < span>< a>< p>